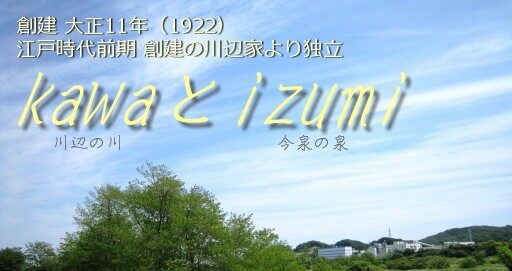江戸城天守台と江戸城本丸跡



番所とは警備の詰所を意味します
鉄砲百人組と呼ばれた甲賀組・伊賀組・根来組・二十五騎組が
昼夜交替で詰めていました

同心番所・百人番所・大番所の3つが現存
同心番所には同心が詰め、主に登城する大名の供の監視をした



大奥跡から本丸跡全体を望む
江戸城の本丸跡・二の丸跡は、明治維新後、東京鎮台工兵作業場などに使われていましたが、
皇居造営後は、宮内庁の役所や内親王の呉竹寮など、皇室の施設として使用されてきました。
しかし、戦後、昭和天皇の発案により、武蔵野の俤を伝える庭園(皇居東御苑)として整備され、
昭和43年(1968)から一般公開されています。
二の丸には、寛永7年(1630)に3代将軍徳川家光の命により、小堀遠州が造ったといわれる回遊式庭園がありましたが、
現在、二の丸庭園では、同じ場所に復元した池を見ることができます。
大広間や大奥などがあった広大な本丸跡は、広い芝生の広場になっていて、親子連れも見られます。


本丸跡の一角には、「忠臣蔵」の浅野内匠頭・刃傷事件でおなじみの松之廊下跡もあります。